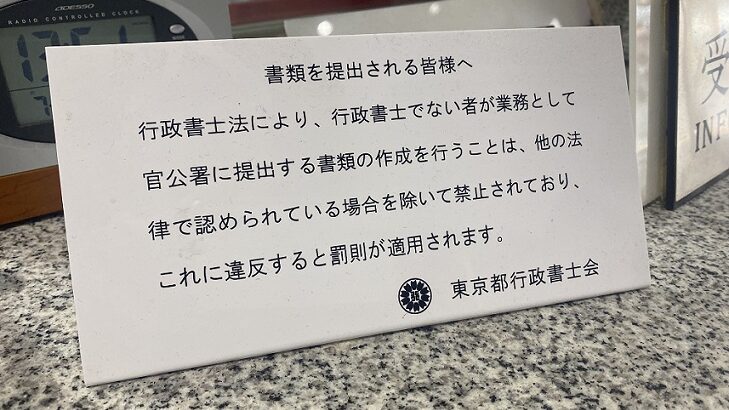非常灯の電気はどのように取ればよいでしょうか?
専用回路? メインブレーカーの一次側? 正解はどのように取ればよいでしょうか。
※結論を知りたい方は最下段のまとめを御覧ください。
私達も現場で電気業者さんや関係者に聞かれることがあり、設置方法については色々な情報が飛び交っています。
非常灯の設置については建築基準施行令126条の5に記載されています。その条文を下に引用します。
第百二十六条の五
前条第一項の非常用の照明装置は、次の各号のいずれかに定める構造としなければならない。
一 次に定める構造とすること。
イ 照明は、直接照明とし、床面において一ルクス以上の照度を確保することができるものとすること。
ロ 照明器具の構造は、火災時において温度が上昇した場合であつても著しく光度が低下しないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
ハ 予備電源を設けること。
ニ イからハまでに定めるもののほか、非常の場合の照明を確保するために必要があるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
二 火災時において、停電した場合に自動的に点灯し、かつ、避難するまでの間に、当該建築物の室内の温度が上昇した場合にあつても床面において一ルクス以上の照度を確保することができるものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。
非常灯の電源は告示1830号に準じて取り付ける
建築基準施行令126条の5には非常灯の設置についての基準が書かれていますが、電源の取り方については記載されていません。では、その基準はどこに記載されているかと言うと 建設省告示台1830号 に記載されています。
この告示は「非常用の照明装置の構造方法を定める件」についてのもので、非常照明の器具や配線などについて書かれています。告示を下に引用します。
第二 電気配線
一 電気配線は、他の電気回路(電源又は消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第七条第四項第二号に規定する誘導灯に接続する部分を除く。)に接続しないものとし、かつ、その途中に一般の者が、容易に電源を遮しや断することのできる開閉器を設けてはならない。
二 照明器具の口出線と電気配線は、直接接続するものとし、その途中にコンセント、スイッチその他これらに類するものを設けてはならない。
三 電気配線は、耐火構造の主要構造部に埋設した配線、次のイからニまでのいずれかに該当する配線又はこれらと同等以上の防火措置を講じたものとしなければならない。
イ 下地を不燃材料で造り、かつ、仕上げを不燃材料でした天井の裏面に鋼製電線管を用いて行う配線
ロ 準耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されたダクトスペースその他これに類する部分に行う配線
ハ 裸導体バスダクト又は耐火バスダクトを用いて行う配線
ニ MIケーブルを用いて行う配線
四 電線は、六百ボルト二種ビニル絶縁電線その他これと同等以上の耐熱性を有するものとしなければならない。
五 照明器具内に予備電源を有する場合は、電気配線の途中にスイッチを設けてはならない。この場合において、前各号の規定は適用しない。
告示1830を読んでいくと、次のようにまとめることができます。
・他の電気回路と同じにしてはならない(専用回路)
・照明器具以外のコンセントやスイッチと接続してはならない
・耐火、不燃措置を設けなければならない
・電線は耐熱性を有しなければならない
このまとめからわかるように、「専用回路を設ける」はこの部分からきています。
専用回路は本当に必要なのか?

告示文を見る限り、専用回路が必要と解釈ができます。専用回路ということは非常灯回路以外に他の負荷を何も設置してはいけないということになります。
電気回路の仕組みがわかる方はピンとくると思いますが、非常灯は非常時に点灯する設備のため、通常は消灯している性質を持っています。※照明付き非常灯を除く
本来であれば、通常使用している電灯が消灯したタイミングで非常灯が点灯することが理想的です。もし非常灯回路が専用回路とした場合、メインブレーカーが落ちない限り非常灯はつかないことになります。言い換えれば、もし通常の電灯回路に何らかの異常があり、ブレーカーが落ちても、非常灯が作動しないことになります。
そうなると非常灯の効果がなくなってしまいます。そのような状況に適応するためにはどうすればよいでしょうか?
告示をよく読んでみると、5号にこの場合を想定した文章があります。
五 照明器具内に予備電源を有する場合は、電気配線の途中にスイッチを設けてはならない。この場合において、前各号の規定は適用しない。
この文章は「バッテリーを搭載した非常灯」を設置する場合は、途中にスイッチを付けるのはダメだけど、専用回路や耐火、不燃措置を取らなくていOKと書いてあります。
つまり、電灯回路から分岐してもOKという解釈ができます。その他、電灯回路でなく、コンセント回路からでもOKということになります。
非常灯の効果を発揮させるためには電灯回路から取るのが良さそうです。
では、なぜこのような告示があるのか?
非常灯は器具自体に「非常灯にバッテリーを搭載している」ものと「搭載されていない」ものがあります。告示では「バッテリーを搭載していない非常灯」を想定して書かれていて、例外規定としてバッテリーを搭載した非常灯という感じになります。
「バッテリーを搭載していない非常灯」とは
器具自体にバッテリーを搭載していない非常灯がどのようなものかと言うと、自家発電設備や蓄電池設備を装備した建物に設置するもので、その建物に停電が起こると、非常灯の専用回路に電気が流れ非常灯を点灯させるというものです。
この非常灯は、電源を一括管理しているため、専用回路が必要になり、配線には耐火、耐熱処理が必要になるのです。もし火災が起こり、耐火ケーブルでないビニル配線類は、短時間で火の熱により被覆が溶けて動線がむき出しになります。
動線がむき出しになると電線が早いタイミングでショートし非常灯回路が機能しなくなります。このような事態を回避するために、専用回路や耐火、耐熱処理関係を告示1830により定められているのです。
民泊物件を想定したコンセント式の非常灯

民泊を想定したコンセントタイプの非常灯もラインナップに加わっています。この非常灯の特徴はコンセントを差すことで非常灯として機能します。コンセント回路から電源を取るため、このコンセント回路のブレーカーが落ちるか、メインブレーカーが落ちるかにより非常灯が作動します。
電灯回路が落ちたタイミングでは非常灯に切り替えられませんが、告示の基準をクリアしているため適法な設置となります。コンセントタイプの非常灯は、電気配線やブレーカーへの接続が不要なため、電気工事士の資格が不要です。
このコンセントタイプの非常灯の設置根拠も告示1830にしっかり記載されています。
三 照明器具内に予備電源を有し、かつ、差込みプラグにより常用の電源に接続するもの(ハにおいて「予備電源内蔵コンセント型照明器具」という。)である場合は、次のイからハまでに掲げるものとしなければならない。
イ 差込みプラグを壁等に固定されたコンセントに直接接続し、かつ、コンセントから容易に抜けない措置を講じること。
ロ ソケット(第一号ハ(2)に掲げるLEDランプにあつては、接続端子部)から差込みプラグまでの電線は、前号に規定する電線その他これらと同等以上の耐熱性を有するものとすること。
ハ 予備電源内蔵コンセント型照明器具である旨を表示すること。
コンセントタイプは抜けてしまうおそれがあるので、抜けないような仕組みを取る必要があります。画像のパナソニック社製品ではコンセントに蓋が設けられ告示に書かれている内容通りの設計となっていることが分かります。
非常灯設置と誘導灯では根拠法令が違う

今回のテーマとは少しそれますが、非常灯と誘導灯の設置基準については根拠となる法令が異なります。非常灯は建築基準法令が根拠となりますが、誘導灯については消防法令に基づいた設置が必要になります。
電源の取り方については若干違いがあるので、詳しくは別の記事で紹介したいと思います。ちなみに、誘導灯は非常灯とは異なり専用回路が必要かつ、漏電ブレーカーの2次側から受電してはならないという決まりがあります。
誘導灯は避難経路を示し、人命存続の命綱という性質がるため、簡単に電気の供給を止めるわけにはいきません。誘導灯自体にバッテリーを搭載していますが、電源の供給自体が停止することのないように設置し、それでも万が一、停電した場合に備えて予備電源にて点灯する設計となっています。
非常灯をブレーカーの一次側で受電するとどうなるか?
まず、ブレーカーの1次側を説明します。
よく言われるブレーカーの一次側を正確に言うと「漏電ブレーカーの一次側」のことを指しています。
漏電ブレーカーの回路に漏電が発生するとブレーカーは当然に遮断されます。
一次側から受電するとは、漏電ブレーカーの一時側の端子からIV線などを分岐させるように別の漏電ブレーカーでないブレーカーに接続し、設け各種機器(負荷)を設置する状態のことをいいます。
このような一次取り受電方法は誘導灯や自動火災報知設備をはじめとする各種消防設備で行われる施工方法になります。
ブレーカーの中心にあるブレーカーのレバーを隔てて1次側、2次側とします。ブレーカーを落とすと1次側には電気が流れていますが、2次側には流れなくなります。ブレーカーが機能しているため電気が止まっているからです。
もし電気を一次側から漏電ブレーカーではないブレーカーを経由し、非常灯回路に電源を供給すると、電気回路に電気が流れっぱなしになります。
電源を供給している限り非常灯は消灯し、電源の供給が停止すると非常灯は点灯します。
非常灯の電源を漏電ブレーカーの一次側で取ってしまうと電源が供給されっぱなしになり、非常灯を点灯させるには、地域の停電が起こらない限り機能しないことになります。
通常使用する電気照明が停止したときに非常灯を作動させるためには、漏電ブレーカーの2次側から受電(電灯回路と同じ回路が望ましい)することがもとめられます。
| 非常灯 | 誘導灯 | |
| 専用回路 | バッテリー搭載型は専用回路不要 | 専用回路が必要 |
| 受電方法 | バッテリー搭載型はブレーカーの2次側から受電しないければ非常灯が機能しない | 漏電ブレーカーの1次側受電が必要 |
非常灯と誘導灯は似たような設備なので設置方法について混同しないようご注意願います。
まとめ
・バッテリーを搭載した非常灯は専用回路でなくても良い
・非常灯は電灯回路と同回路から取るのが望ましい
・非常灯と誘導灯は目的と根拠法令が異なるため電源の取り方に違いがある
専用回路が不要のバッテリー搭載型非常灯の紹介
コンセント付き非常灯(無資格者でも施工OK)
一般型非常灯(100Φ埋め込み)※電気工事士資格が必要
一般型非常灯(露出型)※電気工事士資格が必要
関連記事:民泊対応のための非常灯を設置してみた